08.古墳時代の道具
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2706
石製模造品

大きさわずか数cmのミニチュアの石製品で、剣や鏡、玉などを模したものです。祭壇に置いたり、木の枝につるしたり当時の祭祀(お祭り)に使ったものだと推定されます。道仏遺跡では石製の玉の代わりに土製の玉が使われていたようです。
土錘

棒状のおもりで川魚等をとるための網におもりとして付けられていました。道仏遺跡は川や沼辺に位置していたと考えられます。
紡錘車

糸をつむぐ道具であるはずみ車にあたるものです。
カマド
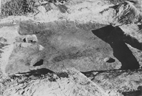
縄文時代から古墳時代中期(1,550年前頃)までは、竪穴住居の中央部付近に炉が造られ、そこで煮炊きを行いましたが、古墳時代後期(1,500年前)になると住居跡の奥壁にカマドが造られるようになります。カマドの出現により甕(かめ)の形も丸みのあるものから長細いものに変わり、蒸す道具である甑(こしき)が竪穴住居跡からたくさん出土するようになります。またこうした道具の変化だけでなく、カマドの出現によって、それに伴う祭りや世界観など人々の生活様式が大きく変化したことがうかがわれます。
埴輪

一般的に埴輪というと人物埴輪や馬形埴輪が有名ですが、古墳から出土する埴輪のほとんどが筒形をした円筒埴輪です。
埼玉古墳群の将軍山古墳や目沼瓢箪塚古墳の発掘でもわかりますが、円筒埴輪は古墳の墳丘上に1列または数列にわたり整然と並べられていました。
お問い合わせ
宮代町役場教育推進課文化財保護担当(郷土資料館)
電話: 0480-34-8882
ファックス: 0480-32-5601
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
