06.古墳時代の遺跡
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2693
宮代町では弥生時代の遺跡は見つかっていませんが、古墳時代前期(約1,650年前)になると山崎山遺跡や地蔵院遺跡で集落が確認されています。特に山崎山遺跡では住居跡だけでなく、埼玉県で最古の鍛冶工房(下写真)が1軒発掘されました。さらに、古墳時代後期(約1,500~1,300年前)になると道仏遺跡で大型の集落が営まれたようです。この遺跡からは、お祭りに使用された滑石製のミニチュア石製品である剣形品や有孔円盤が出土しています。道仏遺跡から谷を隔てた南東側には宮代町で唯一確認されている姫宮神社古墳群があります。出土したハニワ片は約1,500~1,450年前ですので、もしかしたら、道仏遺跡にあったムラの首長やその一族の墓が姫宮神社古墳群である可能性もあります。

古墳時代の遺跡
山崎山遺跡
道仏遺跡

道仏遺跡は道仏地区区画整理事務所建設に伴う事前の発掘調査として平成9年度に実施されました。調査の結果、古墳時代後期(6世紀中頃)の重複する住居跡7軒、土坑1基が検出されました。調査区全体が重複する住居跡の覆土で覆われていることや、小規模の発掘調査のため詳細は不明ですが、剣形品や有孔円盤などの石製模造品が多数出土したことから、この遺跡の重要性がうかがわれます。住居跡の1つは焼失住居跡で茅材や建築部材も多数検出されました。多くの土玉、土錘、紡錘車等の土製品、石製品も多数出土しています。住居跡の多くはいずれも北東側に竈があると推定されます。
姫宮神社古墳

道仏遺跡と姫宮古墳
沼や湿地に囲まれ、半島状突き出した台地の先端部に古代の道仏ムラがあります。ムラの周辺にヒエやムギ、マメなどを栽培した畑があったと推定されます。台地周囲の湿地の一部で水田が営まれていました。
ムラ内には首長の屋敷や有力者の家である平地式住居や穀物を蓄えた高床倉庫、庶民の住居である竪穴住居、滑石製模造品を作っていた工房などもありました。ムラ南東部、湿地を挟んだ姫宮地区には、ムラの首長や有力者を葬った古墳が点在し宗教的な場所として重要視されていました。
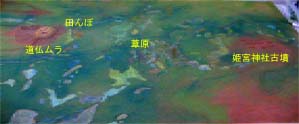
お問い合わせ
宮代町役場教育推進課文化財保護担当(郷土資料館)
電話: 0480-34-8882
ファックス: 0480-32-5601
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
