08 伊勢参詣手形・廻状・名字帯刀仰付状
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2670
伊勢参詣手形
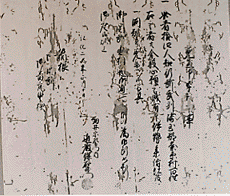
弘化2年(1845)に東粂原村の農民が伊勢神宮参詣のため知行主の旗本細井宗左衛門家臣近藤保左衛門から箱根関所番衆あてに出されたものです。江戸時代、関所は「入り鉄砲に出女」というように人々の行き来を厳しく取り締まっていたため、領主から出された手形がないと関所を通過することができませんでした。
廻状
同一の文書を数人の受取者に回覧の方法で送る文書をいいます。領主から支配下の村々に法令の伝達や村落相互の連絡にこの方法が取られました。受け取った村は捺印をし御用留に記録し、次の村に送ったのです。百間村は最後の村であったためこの廻状が残されたようです。
この文書は文久3年(1863)の七卿落ち関連のもので、三条実美ら急進(討幕)派の公卿7名は公武合体派の公卿により失脚させられ、京都から長州藩に脱走しました。この時全国の村々に廻状が通達されました。
名字帯刀仰付状
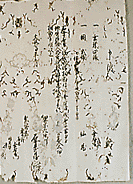
旗本細井宗左衛門の家臣石井甚兵衛から東粂原村の名主幸右衛門あてに名字と帯刀を許すことを認めた文章です。
お問い合わせ
宮代町役場教育推進課文化財保護担当(郷土資料館)
電話: 0480-34-8882
ファックス: 0480-32-5601
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
