06発掘された縄文時代のむら3
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2555
金原遺跡9号住居跡
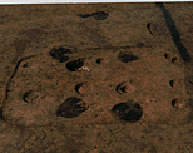
縄文時代早期条痕文期(約7,000年前)の住居跡で、4.5m×2.8mを計る長方形をした住居跡である。12本の柱跡が発掘されたが、炉跡は検出されなかった。この住居跡の近くから屋外で煮炊きを行った炉穴が確認されている。
金原遺跡11・12・13・14・17号住居跡

いずれも縄文時代後期称名寺期(約3,500年前)の住居跡で5軒の住居が重なって発掘された。近世の道路状遺構などで壊されていたため、あまり残りのよい状態ではなかったが、多数の土器が出土している。耕作のため掘り込みはほとんど残ってなかったが17号住居を切って11・12号住居が構築されていたことが確認されている。柱穴の底からはクルミも出土している。
金原遺跡15号住居跡

縄文時代後期称名寺期(約3,500年前)の住居跡で平面の形は柄鏡形を呈する。主体部の直径5.4mを計る円形で、柄部は2.3mを計る。柱穴は23本を数える。中央やや西側で炉跡を検出した。7号住居跡東側10mの位置にある。234・235号土坑に切られる。
金原遺跡16号住居跡

縄文時代後期称名寺期(約3,500年前)の住居跡で平面の形状は柄鏡形を呈する。主体部は直径4.5mを計る円形で、柄部は1.3mを計る。柱穴は22本を数える。炉跡は主体部北側で検出された。直径70cmを計るやや大型の炉跡で被熱部直上で大型の磨製石斧が出土した。236・237号土坑に切られる。
金原遺跡18号住居跡

縄文時代後期称名寺期(約3,500年前)の住居跡で平面の形状は長径5.6m、短径5.4mを計る円形を呈する。柱穴は8本を数え等間隔に配置されていた。中央部より炉跡が検出されている。
お問い合わせ
宮代町役場教育推進課文化財保護担当(郷土資料館)
電話: 0480-34-8882
ファックス: 0480-32-5601
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
