05先土器時代の金原遺跡
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2532
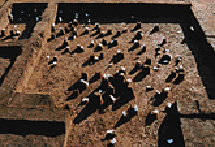
金原遺跡に人々が住み始めたのは今から約20,000年前と推定される。この頃は、浅間山などの火山活動が活発で、多量の火山灰が降り積もった。これが「赤土」すなわち関東ローム層と呼ばれる土である。この「赤土」の中から当時の人々が使った道具が発見されている。金原遺跡では、約20,000年前のナイフ形石器や約14,000年前のと呼ばれる縦長の石器を作った細石器の製作跡(左写真)が1か所確認された。この製作跡からは、約30点もの細石刃が出土している。これは、埼玉県東部地区に広がる大宮台地では町内の逆井遺跡に続く2例目の貴重な発見である。また、平成10年8月に確認された2号細石器ブロックからは砂川期のナイフ形石器1点と細石刃7点が共伴して出土した。

現在まで6点のナイフ形石器が出土している。この石器は縦長の剥片の鋭利な一辺を刃部としてナイフ形に作り出されたものである。一般的に皮を剥いだり槍の先に付けたものといわれている。金原遺跡で出土したナイフ形石器は黒曜石とチャートと呼ばれる石材を用いて作られている。こうした石材は宮代町付近にはないため、ほかの地域からはるばる運ばれてきたと考えられる。

細石器の製作跡から約30点もの細石刃が出土した。この石器は約3cm内外の小型の剥片を利用した石器で木や鹿の角・骨などの軸の両側縁に10数個はめ込み使用した。今日でいう「包丁」的な道具として使われたようである。

石の剥片などの一端を加工した石器である。木を削ったり、皮をなめすなどに使われたと考えられている。
お問い合わせ
宮代町役場教育推進課文化財保護担当(郷土資料館)
電話: 0480-34-8882
ファックス: 0480-32-5601
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
