05旧石器・縄文時代の道具2
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2509
浮き

軽い石を加工して作った石器です。網を使用して魚を捕獲する際に使われた道具です。宮代町周辺では狩猟に加えて漁労も盛んに行われていたようです。
耳飾り
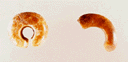
今でいうピアスのようなものですが、耳を通す穴の部分は大きく、耳たぶ全体にはめ込むようにつけていました。なめらかでつやのある石や土を材料に作られています。各遺跡からの発見が少ない貴重なものです。
ペンダント

縄文時代にはさまざまなアクセサリーが用いられ、ペンダントはその一つにあたります。縄文人が好んだといわれるヒスイや粘土を焼いたものなどで作られています。身を飾るだけではなく、精神文化の一端をあらわしていたといわれています。
土器片錐
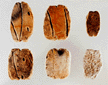
縄文時代、土器の破片を加工して作った魚網のおもりとなる道具です。魚網の先端にいくつかの土器の破片を用いたおもりをつけて沈め、魚を捕っていました。そのため両端に網をつけるための切り込みが入っています。
ミニチュア土器

輪積みなどの方法により作り、ヘラを用いて整形した土器とは異なり、小さな粘土塊を手だけによって形づくられた小さな土器です。一般の土器とは異なり祭祀用具として使われたものと考えられています。
土製品


有孔球状土製品やリング状土製品など立体を呈する土製品は、主に縄文時代中期から晩期にわたって多く用いられるようになりました。ことに、有孔球状土製品は中央に縦に貫通した穴があります。アクセサリーや呪術具、土錘などいろいろな用途が考えられますが、どのように用いたのかは明らかではありません。
ふた

金原遺跡の縄文時代後期初頭の住居跡(第2号住居跡)から出土している土器のふたです。
お問い合わせ
宮代町役場教育推進課文化財保護担当(郷土資料館)
電話: 0480-34-8882
ファックス: 0480-32-5601
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
