「農のあるまちづくり」における市民参加の取り組み
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:405
はじめに
「農のあるまちづくり」は平成6年、職員プロジェクトによる試行錯誤からスタートした。宮代町にある地域資源をどう今後のまちづくりに行かしていくか、がテーマのひとつ。メンバーで議論して到達したひとつの答えは「水田や屋敷林、用水路」、平凡で見慣れたものにこそ、他にない価値があるのではないか、というひとつの仮説だった。これをよりどころとして「計画」を作って、まちづくりを進めていこう、というのが筋書きだった。
農のあるまちづくりが必要なのは理解できた。そのための計画を行政としてつくるのも必要だ。けれども、単に計画を作って、それだけでいいのだろうか。「計画を作ってから行動に移ればいい」「行動を繰り返しながらでないと、肌で感じることはできない、机上だけの計画は意味がない」など、メンバーで議論。「とりあえずやって見る派」が大勢を占め、宮代町の中にある「農」を題材に「市民参加」をスタートした。
農のあるまちづくりが必要なのは理解できた。そのための計画を行政としてつくるのも必要だ。けれども、単に計画を作って、それだけでいいのだろうか。「計画を作ってから行動に移ればいい」「行動を繰り返しながらでないと、肌で感じることはできない、机上だけの計画は意味がない」など、メンバーで議論。「とりあえずやって見る派」が大勢を占め、宮代町の中にある「農」を題材に「市民参加」をスタートした。
巨峰市
「進修館のぶどう棚」にはお盆のころには巨峰が実をつけるが、食べるのは一部のスタッフとカラス。もったいなくない?そもそも進修館に巨峰があるのは何故?という疑問が浮かぶ。
ということで「巨峰市」を実施、町の巨峰組合にも声をかけて「巨峰」の販売も行った。写真は「巨峰」があたるビンゴ大会の様子。用意した巨峰はすぐに売り切れてしまった。「こんなに巨峰が人気があるなんて」(平成6年9月)
ということで「巨峰市」を実施、町の巨峰組合にも声をかけて「巨峰」の販売も行った。写真は「巨峰」があたるビンゴ大会の様子。用意した巨峰はすぐに売り切れてしまった。「こんなに巨峰が人気があるなんて」(平成6年9月)

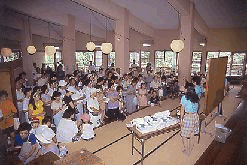
水田オーナー
下野田逆井土地改良区において「水田オーナー」を実施したところ、30家族100人の応募があった。指導者は地元農家の皆さん。そのほか「そば打ち体験」などのイベントも行った。
「田植えを体験」するだけで、なぜこんなに人が参加するのか?は、役場職員にとっても、農家にとっても、その後、農のあるまちづくりを進める上での原点になった。(平成7年6月)
「田植えを体験」するだけで、なぜこんなに人が参加するのか?は、役場職員にとっても、農家にとっても、その後、農のあるまちづくりを進める上での原点になった。(平成7年6月)


畑のオーナー
水田オーナーの姉妹編として「畑のオーナー」も実施。「植えるのと収穫するの」だけの参加だったが、こちらも参加者は多かった。
「自分が食べる野菜を自分で収穫する」のは農家にとっては当たり前だが、農家でない方には意外な発見だったようだ。
「自分が食べる野菜を自分で収穫する」のは農家にとっては当たり前だが、農家でない方には意外な発見だったようだ。

特産品開発
「街おこし研究会」の呼びかけで町の特産品開発として実施。全国からモロヘイヤ料理のレシピを公募し、レシピも作成した。
モロヘイヤふりかけ、モロヘイヤアイスは商品化された。
モロヘイヤふりかけ、モロヘイヤアイスは商品化された。
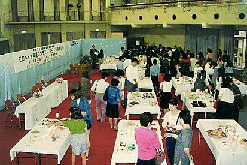

巨峰クラブ
農のあるまちづくりに賛同した、町民による「街おこし研究会」が中心となり、「巨峰クラブ」を結成、巨峰の手入れや収穫を手伝うという「援農」の仕組みの始まりとなった。(平成8年4月)
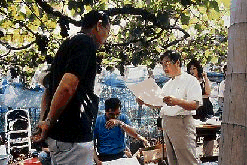

桜市
「農産物の直売」「巨峰わいん」など、農業者と商業者の連携が必要であることを痛感。ごく普通の野菜やくだものを「消費者」にどう届けるか、その実験の始まり。この試みは後日、マーケット計画につながり、「新しい村」に続く道のりのスタートとなった。(平成7年4月)
桜市がきっかけで各地に直売所ができた。地元で取れた「生産者の顔」が見える野菜は、「曲がっていても」消費者には好評だった。その2ヶ月前には「街おこし研究会」の皆さんによる「桜の木のオーナー制度」が実施され、70組の市民の皆さんが商工会前の道路に桜の木を植えた(写真右)。
桜市がきっかけで各地に直売所ができた。地元で取れた「生産者の顔」が見える野菜は、「曲がっていても」消費者には好評だった。その2ヶ月前には「街おこし研究会」の皆さんによる「桜の木のオーナー制度」が実施され、70組の市民の皆さんが商工会前の道路に桜の木を植えた(写真右)。


農のあるまちづくりシンポジウム
こうした取り組みの中間報告、というか、皆でガンバロー会となった「農まちシンポジウム」。約700人の参加者があり、壇上に上がった市民だけでなく、客席でも「農のあるまちづくり」を進めていこうという機運と連帯感に包まれていた。(平成7年11月)


巨峰ワイン
巨峰市も毎年開催し、巨峰農家の皆さんにももだんだん関心をもってもらえるようになってきた。皆さんの努力と汗の結晶をオールシーズン活用できないか、という考えで作られたのがワイン。産業祭では一番の人気品。巨峰ワインづくりには町民のボランティアも参加。(平成7年9月)


市民農園探検隊
策定しようとする「農まあるまちづくり計画」の2本柱は
農のあるまちづくりのシンボルとなる空間づくり、
地産池消の拠点となる拠点づくり
例によって、市民と「探検隊」を組織して、他自治体の「市民」農園を視察。「こんな市民農園がいいね」を話し合った(全3回)。後の「新しい村」につながっている。
平成10年には「池のある公園探検隊」も組織され、これは現在の「新しい村」の「池のある公園部分」になっている。(平成8年3月) こうした市民参加の取り組みを繰り返しながら、気づき、発見し、教えられ、仲間が増えて、「農のあるまちづくり計画」が完成した。(平成10年2月)
「新しい村」は平成13年にオープンした。
農のあるまちづくりのシンボルとなる空間づくり、
地産池消の拠点となる拠点づくり
例によって、市民と「探検隊」を組織して、他自治体の「市民」農園を視察。「こんな市民農園がいいね」を話し合った(全3回)。後の「新しい村」につながっている。
平成10年には「池のある公園探検隊」も組織され、これは現在の「新しい村」の「池のある公園部分」になっている。(平成8年3月) こうした市民参加の取り組みを繰り返しながら、気づき、発見し、教えられ、仲間が増えて、「農のあるまちづくり計画」が完成した。(平成10年2月)
「新しい村」は平成13年にオープンした。


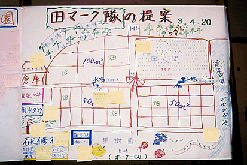


みやしろっ子
「稲作研究会」が減農薬コシヒカリの栽培に取り組み、お米の愛称も町民から募集した。その結果「おいしいお米をたべて元気に育て」という願いをこめて「みやしろっ子」に決定
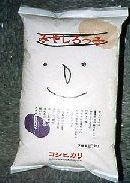
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課政策調整担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線222(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
