第4次宮代町総合計画基本構想 (案)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:744
PDF版の資料

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
第1章 まちづくりの目標
まちの将来都市像
将来都市像は、市民と行政がともにまちづくりを進めていく上で、共通にイメージできる方向を示すものであり、まちの個性が表現され、将来に向けたまちづくりの指針としての意味が込められています。
今後、国全体で人口減少、高齢化が進んで行く中で、今以上に魅力あるまちを創りあげ、一人ひとりが生きがいを持って日々の生活を過ごして行くためには、互いの人権を尊重し、町中のさまざまな主体がそれぞれの役割を担い、連帯しながら、宮代町の地域資源を最大限に活かしたまちづくりを進めていく必要があります。そこで、宮代町が目指すべき10年後の将来都市の具体像を以下のように定めます。
- 人口減少、超高齢社会に対応できるまち
- 今ある強みを最大限に活かせるまち
- 「農」のあるまちづくりを全面展開するまち
- 多様な主体により公共が運営されるまち
この4つの具体像を包括的に表現する将来都市像を、「みどり輝くコンパクトシティ」とします。
計画期間
平成23年度~平成32年度
将来人口
平成32年度の目標人口を35,000人とします
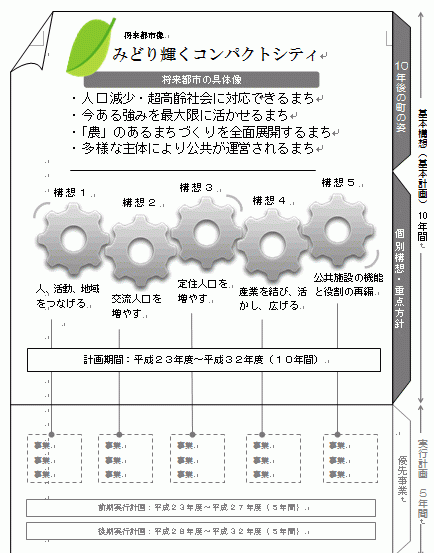
基本構想(基本計画)10年間
10年後の町の姿
将来都市像 みどり輝くコンパクトシティ(※1)
将来都市の具体像
- 人口減少・超高齢社会に対応できるまち
- 今ある強みを最大限に活かせるまち
- 「農」のあるまちづくりを全面展開するまち
- 多様な主体により公共が運営されるまち
※1 地域社会を重視し、既存の都市機能を効率よく活用する持続可能なまち
個別構想・重点方針
- 構想1
人、活動、地域をつなげる - 構想2
交流人口を増やす - 構想3
定住人口を増やす - 構想4
産業を結び、活かし、広げる - 構想5
公共施設の機能と役割の再編
計画期間
実行計画 5年間
前期実行計画
後期実行計画
第2章 土地利用方針
基本的な考え方
土地は、市民のための限られた貴重な資源であり、「住む、働く、憩う、育てる、ふれあう」といった諸活動にとって共通の基盤であるため、地域の発展や市民生活と深い関わりを持っています。土地利用にあたっては、将来都市の具体像を実現するために都市の均衡ある発展、自然との共生、安全で快適な環境の確保を図ることを基本として、有限な資源の保全に努めながら総合的・計画的に進めていく必要があります。
基本方針
- 既存住宅地
東武動物公園駅、和戸駅、姫宮駅周辺の市街地では、土地の有効利用および既存住宅の空き家、空き部屋を活用し、新たな定住人口の受け入れを図っていきます。 - 新住宅地
既存市街地に隣接する新住宅地は、新たな流入人口の受け皿として土地区画整理事業などの面的整備を行い、農空間と連携した魅力ある市街地を創出します。 - 中心商業地
商業施設の集積を誘導するとともに、公共施設や市民活動施設を含めた観光資源を有効に活用し、活気と賑わいのある「歩いて楽しい地域」を形成します。 - 近隣商業地
3つの駅を中心に商業施設などの集積を誘導するとともに、土地の有効利用および空き店舗を活用し住宅地に密着した地区の生活拠点を形成します。 - 工業地
周辺環境に配慮した工業施設の集積を図ります。 - 公園・緑地
「新しい村」をはじめ、公園、河川、水路の緑化を図り、グリーンツーリズムの舞台として魅力ある空間を形成していきます。 - 集落環境保全ゾーン
農家住宅を中心として身近なサービス施設を含む集落環境を総合的に保全・育成していくとともに、「農」の風景や緑豊かな環境を保全していきます。 - 営農環境保全ゾーン
農業、農地の担い手を育成、支援しながら、良好な営農環境を総合的に保全・育成していきます。 - 土地利用検討ゾーン
周辺の居住環境や営農環境との調和を保ちながら、宮代町に適した産業への活用も含めた将来の土地利用を検討していきます。
土地利用構想図
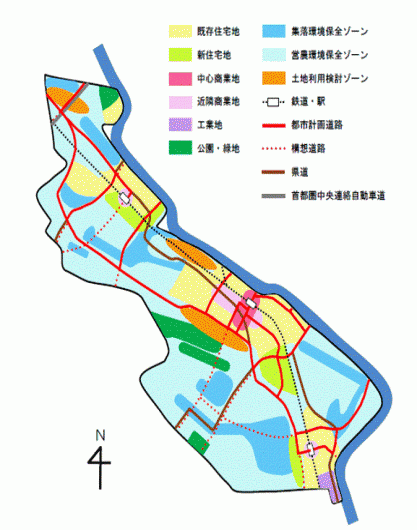
第3章 重点構想
構想1 人、地域、活動をつなげる
一人ひとりの「顔」が見え、「つながり」を実感できる社会は、そこで生活する人に、モノや制度以上の安心感や充実感をもたらすことができます。特に人口減少、超高齢化が進む中では、買い物難民対策、高齢者への見守り、子育て支援、バリアフリー化など、多くの分野においてこうした社会の実現が求められています。
これらを実現する糸口となるのが、第一に地域コミュニティです。
地域におけるマンパワー、ボランティア力は重要な要素です。しかし、行政が「側面支援」というあいまいな手法で関わるならば、地域コミュニティの力を最良な形で引き出すことは難しく、現実を前に進めることはできません。行政はこの力を引き出すための動機付けとなる積極的な施策を展開する必要があります。そして、継続的な地域活動の推進役となるキーマンを探し出すことも重要です。
そして第二に地域を横断する形で、同じ趣味や目的を持つ者同士のつながりが町の中にあることが重要です。
子育てネットワークや高齢者をサポートするボランティアのネットワーク、街おこし、観光、産業などの市民活動や生涯学習活動が、町の中のさまざまな場面で展開され、時には行政と、時には自治会と、あるいは団体同士が共同の作業につけるよう、その実現に向けた作業を始めます。行政主体の市民活動スペースや進修館の運営も見直していきます。
方針1 自治会内の自主活動が地域を強くし、町の活力を生む
方針2 小さな拠点(集会所)からの新たな展開
方針3 市民による市民活動支援
町を横断する市民活動やNPO活動、趣味の活動を盛んにし、それぞれがつながり協力できるネットワークづくりを進めます。また、そうした市民の活動を他の市民や市民グループがみんなで支援していく仕組みを構築していきます。
方針4 大きな拠点(進修館)からの新たな展開
方針5 拠点どうしの連携による大きなコミュニティ
子育てや高齢者を地域でサポートする町内三世代タウンの実現を目指し、各地域の拠点や市民活動が、必要に応じて結びつくネットワークを構築します。また、主要施設を結ぶ町内循環バスは高齢者の利便性を高め三世代タウンの交通機関として運行します。
構想2 交流人口を増やす
地域経済や市民活動の活性化、そして定住人口を増やしていく手がかりとして重要な要素となるのが町外からの交流人口です。ここに着目するならば、宮代町には東武動物公園、新しい村、日本工業大学などの地域資源や3つの駅があり、近隣の自治体に比べて優位にあると言え、宮代ならではの魅力を生かし人の流れを作り出していくことで町の活力を高めていくことができます。
まずは、宮代町が進めている「農」のあるまちづくりを対外的にアピールする施策を積極的に展開していきます。そのため「新しい村」「屋敷林」「山崎山などの里山」をテーマにしたメディア戦略が必要です。さらに、「東武動物公園」「ユニークな建築物」「(地勢としての)首都圏のグリーンフロント」などさまざまな要素を総合的な力とするための戦略を立て、日帰り観光やグリーンツーリズム事業を推進します。これにより、交流人口の増加を図っていきます。
交流人口の増加は、さまざまな分野への刺激となりまちづくり全体の活性化と、町全体のさらなる魅力向上が期待できます。また、交流人口を大幅に増やすことは、その中から「宮代町に住んでみよう」と思う、多くの宮代ファンを獲得することにもつながります。
方針1 歩いて楽しい地域づくり
東武動物公園駅、進修館、木造庁舎、笠原小学校、東武動物公園、新しい村といった観光資源が集まるエリアを「グリーンツーリズムゾーン」として集中投資を図り、案内表示等の整備や一人でも家族でも安心して楽しめる環境を整えます。
方針2 農を楽しむグリーンツーリズム
首都圏40キロ圏内という強みを生かし「グリーンツーリズムゾーン」を中心に都心からの日帰りツアーを企画します。このツアーを出発点として、ツアーリピーターや宮代産品の通販購入者を獲得し、交流人口を拡大していきます。
方針3 宮代を知る、伝える
多くの人の力を合わせて、宮代の美しい風景や緑豊かな環境など有形、無形の財産を守っていきます。そのため、町の魅力の見える化を図り、ウェブサイトを活用したり、交流人口の増加を図りながら町外の宮代ファンを増やしていきます。
方針4 市民による観光案内、宮代紹介
来町者の希望に応じて、宮代の魅力や歴史を紹介したり、進修館や笠原小学校、新しい村など見所となる施設の案内を行う観光ボランティアを養成します。また、町の誰もが来町者を温かく迎える心を育てていきます。
構想3 定住人口を増やす
積極的に町の魅力を打ち出し内外に発信していくことで、人口の新規流入や宮代に縁を持つ方の帰町を促し、定住人口の増加を図っていきます。特にこれまで宮代に縁の無かった方には、宮代の特長や良さを知ってもらい、交流を重ね安心感を醸成し、定住への動機に結び付けていく必要があります。
子育て世代の定住希望者に向けては、町内の住宅事情とともに、宮代町が取り組んでいる子育て支援策とセットで情報を提供していくことで、安心して子どもを育てられる環境をピーアールしていきます。また、転入者がスムーズに「農」に親しめる環境を整えて宮代町ならではの魅力を最大限に活かし付加価値としていきます。
定住人口の受け皿としては、新規住宅の供給だけでなく現存する空き家・空き地(低稼働・未利用地)の利用を効率的に進めることも合わせて展開していく必要があります。不動産の稼働率や利用状況を調査し、所有者の意向に沿って転貸などを行うマッチング事業を商工会や不動産事業者等の協力を得ながら進めていきます。
方針1 子育て世代増加策
若年世帯の流入を促すため、子育て支援情報とセットで住宅団地内をはじめとする空き家、空き地情報を収集し空き家バンク情報として町内外に発信していきます。
方針2 認定市民農園の提供
町内の貸し農園を調査し、一定の要件を満たす物件を認定市民農園として栽培指導などの付加価値をつけ転入者や町外に向け情報発信します。また、市民農園活用情報などを継続提供し農を媒介としたコミュニティの裾野を広げていきます。
方針3 空き部屋、空き家の多機能活用
学生、単身サラリーマンのホームスティ(下宿)、福祉やコミュニティ分野を含めた事務スペース活用など、貸す側、借りる側双方のメリットを踏まえたマッチングを行い、空き部屋や空き家の利用を促進していきます。
方針4 空き家を活用した2拠点居住から定住へ
町外の方が不安なく宮代町に越して来てこられるよう、宮代暮らしを体験できる環境を整えます。短期的なお試し居住や、都市住民の2拠点居住として町内の空き家を活用し、将来的な定住人口増を図っていきます。
方針5 流入人口の受け皿となる市街地整備
流入人口の受け皿となる区域の整備を進めるため、道仏地区の区画整理に加え和戸駅西口地区の区画整理について調査・検討を進めていきます。また、町の顔となる東武動物公園駅周辺(西口、東口)の整備や、幹線道路、生活道路の整備を進めていきます。
構想4 産業を結び、活かし、広げる
既存産業の発展に力を尽くすとともに、これまでの農林水産業(一次産業)、製造業(二次産業)、サービス業(三次産業)といった産業の枠組みにとらわれず複合することで、新しく生み出される産業形態に目を向けることも必要です。農と商工の連携、福祉や観光、環境などを組み合わせることで、新たな産業を生み出します。そこにビジネスが生まれ、雇用の創出とともに産業全体の活性化も期待できます。
緑豊かな景観の保全にもつながる「農業」の支援として、「農家」「農地」をどうするかの議論と具体的な作業を進める必要があります。一つは代々農業を営んできた人への支援、もう一つは自らの意思で農業者となる人への支援で、これを両輪として進めていく必要があります。宮代町の農地は耕地区画や用排水路などの整備が遅れており、また、集落と農地が混在しています。そこが宮代町の原風景といわれる所以かもしれません。しかし、基盤整備が不十分な農地では作業の効率が上がらず、結果として耕作放棄や相続による農地の細分化が進んでいきます。この解決なくしては「地産地消」の取り組みも砂上の楼閣となってしまいます。農地を活用しやすくするための取り組みを進めます。
一方、商工業は単なる製造業(二次産業)や、サービス業(三次産業)としてではなく、人を含めた町の資源を発展的に活用することで、宮代町に適した形を見出していく必要があります。特に東武動物公園を訪れる観光客や日本工業大学に通う学生に焦点を絞ったサービスには多くの可能性を見出すことができます。また、社会の変化をチャンスとするために関係者関係機関による戦略を構築します。
方針1 地域循環型産業の形成
地元新鮮野菜のデリバリーや高齢者への配食など、売るだけでなく、作る、加工する、届けるなどのサービスを付加価値とし、人、物、金の循環を広げます。また、環境や福祉分野との関わりも含めて生活者のニーズに応える新しい産業づくりを進めます。
方針2 特産品開発とブランド化の推進
町内農作物の加工や希少作物の研究、100%宮代産など特色を持つ特産品開発を進め、企画、生産、加工、販売、ピーアールを一体化し宮代ブランドを確立します。また、近隣自治体との直売所交流や遠隔自治体との特産品交流などを通じ販路を広げていきます。
方針3 農業、農地の担い手支援
多様な農業者支援策や助成制度をウェブ上に一本化するとともに、専業、兼業、定年帰農、新規就農など対象者のニーズに合わせた支援策を構築し、さまざまな担い手を支援していきます。また、生産性の向上に向けた、営農環境の改善に取り組んでいきます。
方針4 趣味やアイデアの商品化と空き店舗活用
市民の趣味、アイデアの商品化や起業を支援します。また、商店街の空き店舗を起業者や市民グループの共同出店、地域のコミュニティサロン、学生のチャレンジショップなどとして多様な活用を図り、町の賑わいを生み出していきます。
構想5 公共施設の機能と役割の再編
宮代町の公共施設は、昭和40年代から50年代にかけて造成された住宅団地を背景として人口が右肩上がりに増えた時代に、その受け皿として建設された小学校、中学校をはじめとして、その時々の行政課題、多様なニーズに応えるために福祉、文化、スポーツなどさまざまな分野で整備されてきました。
このうち学校については、人口構造の変化などにより単純に文部科学省が示した設置基準面積に照らしても、現在ではピーク時の4割程度の床面積で賄える規模に縮小しています。このような中、平成30年代には断続的に小中学校の建て替え時期が訪れます。現在の数、規模のまま建て替えるという選択肢は、財政的にも、また教科指導、クラブ活動などの学校運営面においても合理的ではありません。
むしろ、建て替えにあたっては学校施設単体の更新ではなく、地域コミュニティやさまざまな地域活動を生み出す拠点として、公民館などの機能を併せ持つ施設とすることで、世代を超えた交流、助け合い、地域づくりを進めるきっかけにもなり、財政的な側面だけでなく、地域防災拠点の視点など、今までの公共施設では生み出し得なかった効果を創出することができます。また、公共施設の機能の中には社会状況の変化とともに設置当時の目的に変化が生じ、地域に密着した施設や他の公共施設が役割を果たすことで、今以上の効果を発揮できるものもあります。
こうした考えに基づき、今ある公共施設すべての機能、役割を見直すことで魅力と活力あるまちづくりを進めて行きます
方針1 施設を再編し、地域コミュニティの拠点づくりを進めます
平成30年代から順次建て替え時期を迎える小中学校の再編案を詳細に策定し、地域コミュニティ活動の拠点として多機能化を進めます。また、全ての公共施設を、次代の必要性や社会的役割に合わせた機能の整理を行ない、将来にわたり持続可能な規模への転換を行います。
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課政策調整担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線222(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
