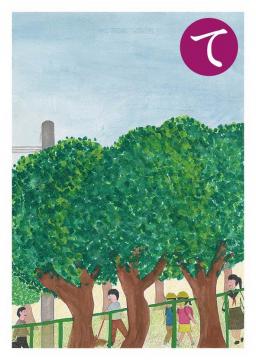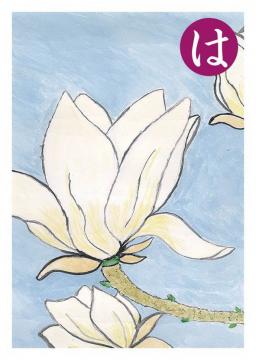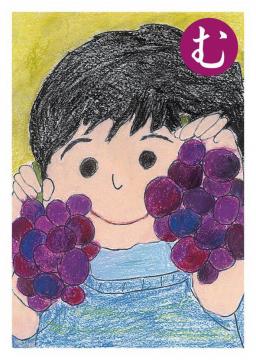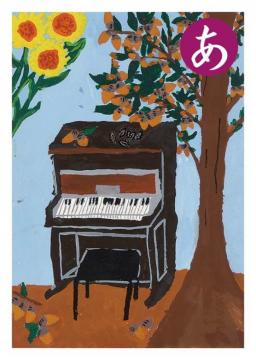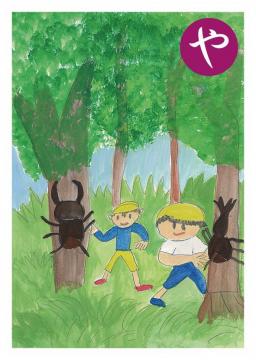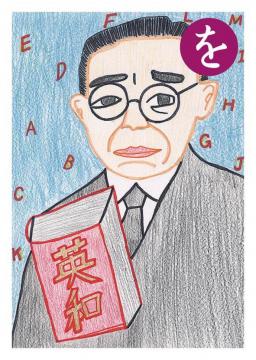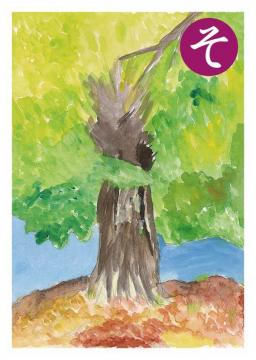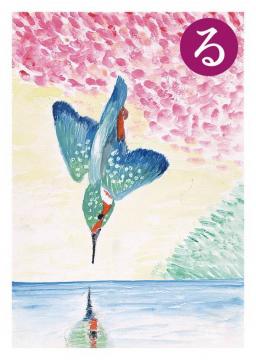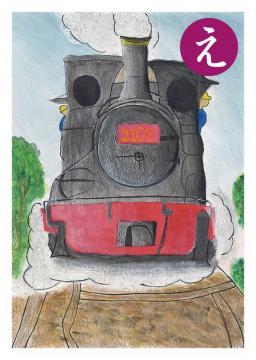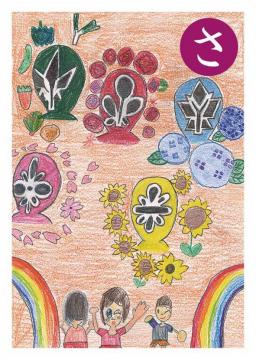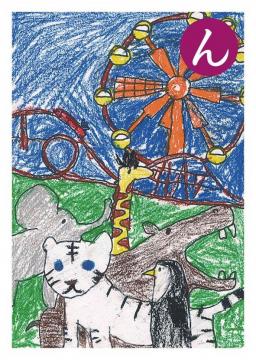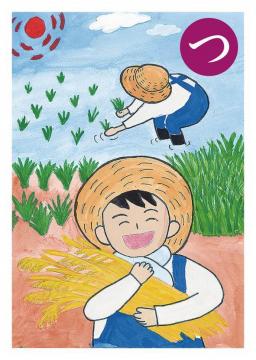新みやしろ郷土かるたの遊び方
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:11152
競技の仕方
競技の種類
(1) 団体競技…3人1組となって、2組で競います。
(2) 個人競技…1人対1人で競います。
競技に用いる札
「新みやしろ郷土かるた」読み札、絵札それぞれ46 枚を使います。
競技に必要な係(各係1~2名)
(1) 進行係
競技運営を良く理解して競技を進行する係。人数が少ない場合は「読み手」が兼ねることもできます。
(2) 読み手
読み札を大きな声ではっきりと読む係。
(3) 審判員
競技を公平に審判し、結果を記録する係。
競技の準備
(1) 競技での遊び方
団体競技は、3人ずつ向かい合い一列に並んで座ります。陣の幅は150 cm以内とし、その中に3人が適当な間隔をおいて並びます。
個人競技は、互いに向かい合って座り、陣の幅は70 cm以内とします。
(2) 持ち札
進行係の合図で真ん中の人がジャンケンをし、勝った側が札をよく切って23 枚ずつ2つの山に分けて、中央に置きます。ジャンケンに負けた側から先に、どちらかの札の山を取り、勝った側は後から取ります。
(3) 札の並べ方
取った札はそのまま並べかえをせず、自陣の前に、団体競技は2段(上段12 枚、下段11 枚)、個人競技は3段(上段8枚、中段8枚、下段7枚)に審判側から並べます。両方の陣の間は3cm離し、札と札の間は上下左右とも1cmほどあけ、札と選手のひざ頭との間は20 cm以上あけます。
(4) 記憶時間
かるたを並べ始めてから5分間を記憶時間とします。
コートの大きさ
札の並べ方
競技
(1)記憶時間が終わると競技に入ります。
(2)「読み手」が「から札【つ】」を2回読みます。これを予告として、その次に読まれる
札から取り始めます。各札は2回ずつ読みます。
(3)手が札に早く触れた方が勝ちです。札の取り方は、押さえても、はじいても、押しても、
引いても構いませんが、故意に飛ばしたりしてはいけません。
(4)取り札が最後の2枚になったら、残った札の状態にかかわらず、中央に30 cmほど
離して横に並べ、対戦組双方の代表1名でこの札を競います。1枚を取った方が、残
りの1枚も取ります。
採点
得点は、1枚1点として計算します。ただし、団体競技の場合は、以下の4種類の「やく札」があり、競技ごとに選んで使います。4種類すべてを使う必要はありません。「やく札」が3枚すべてそろった場合のみ、取った札の枚数のほかに、1種類につき10 点を加算します。団体・個人競技とも、同点の場合は「から札【つ】」を持っている方を勝ちとします。
やく札・から札紹介
シンボル札【て・は・む】
道徳札【あ・や・を】
自然札【そ・や・る】
子ども札【え・さ・ん】
から札【つ】
競技上の注意
札の取り方
札を取るときは、両手を使ったり、札を引っ張りあったりしてはいけません。札が読まれるまでは、手をひざの上に置き、線より前に、頭やひじ、ひざを出さないようにします。また、札を取るときも、使わない手はひざより前に出ないようにします。
お手つき
選手の誰かが、読まれた札以外の札に手を触れたら「お手つき」となり、それまでに取った札の中から1枚を相手に渡します。なお、味方の3人がそれぞれ同時に「お手つき」をしてしまっても、相手に渡す札は1枚とします。ただし、対戦している双方が同時に「お手つき」をした場合と、手持ちの取り札がない場合は、札を渡す必要はありません。
あいこ
札を取る手が重なった場合は、下にある手の人が札を取ります。重なることなく双方同時に札に手が触れた場合は、自陣の人が札を取ります。ただし、その札が「やく札」の場合は「審判あずかり」とします。
その他の注意事項
競技の始めと終わりには、お互いに「礼」をしましょう。また、相手に不満があっても、直接言い争うのではなく、審判を通して意見を述べましょう。
新みやしろ郷土かるたの遊び方をダウンロードできます
新みやしろ郷土かるたの遊び方

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
宮代町役場教育推進課生涯学習・スポーツ振興担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線433、434、435(2階18番窓口)
ファックス: 0480-34-4152
電話番号のかけ間違いにご注意ください!